| 3Frカテーテルによる造影上のTips |
1. mechanical injectionは必須か?
現在,我々の施設では,右冠動脈造影を注入速度2.0-3.0 ml/sec,総量4.0-6.0 ml,左冠動脈造影で注入速度2.0-3.0 ml/sec,総量6.0-8.0 mlで行っていますが,注入時の圧力は300-400 psiにまで上昇します.psiの単位ですと想像のつかない方もいらっしゃると思いますので,大気圧に換算すると20.4-27.2気圧に相当します.これはPCIのバルーンを超高圧拡張する際の圧力に相当します.したがって,manual injectionは筋力トレーニングしだいでは不可能だとはいえませんが,3Frカテーテルの造影にはおすすめできません.
左室造影では,現在,注入速度10 ml/sec,総量30 mlに設定していますが,注入時の圧力は950-1,000 psiにまで上昇します.これは64.6-68.0気圧に相当します.mechanical injectionは必須です.
2. 造影剤の選択は?
できるだけ低粘度の造影剤を選択する必要があります.左室造影(注入速度10 ml/sec,総量30 ml)では,粘度1.0 mPa x secの差でおおよそ最大圧に50 psiの差が生じます.また,造影剤の粘度はかなりの温度変化を起こします.当然高い温度の方が粘度は下がりますので,きちんと37度に管理して使用する必要があります.加温装置の付いていないinjectorは論外です.
3. ピッグテールカテーテルを単独で左室に挿入可能か?
単独で左室に挿入はほとんどの場合不可能です.ガイドワイヤーを左室に入れて,それに沿わせて入れるしかありません.3Frカテーテルはたいへん柔らかいため,左室の心尖部近くまで入れてもあまり不整脈を誘起しないようです.深く安定した位置にポジショニングできると,良好な造影が可能となります.
4. 3Frカテーテルの操作性は?
現在のカテーテルでは,そのままの位置でトルクだけを伝えることはよほど条件がよい場合(血管の走行がまっすぐで素直な場合)を除いては困難です.トルクを伝える唯一の方法はカテーテルを引き抜きながら回転させることです.これは,Judkinsの原法とはまったく反対の操作になります.状況によっては,ガイドワイヤーを入れたままで操作をする必要もありますが,4Frのカテーテルによる冠動脈造影やPCIに習熟された術者であれば問題なくできると思います.
5. 冠動脈造影時のカテーテルの位置は?
通常の冠動脈造影よりも多少深めの位置にポジショニングした方が安定した造影が得られます.
| 3Frカテーテル使用の際のエアー抜き |
当院で行っている造影の際の回路の準備手順についてご紹介したいと思います.東京医科大学の伊藤茂樹先生からインジェクターを使うとエア抜きが難しいとのご指摘があり,参考になればと考え,手順を整理してみました.
| 1. 造影回路 |
現在,当院では,圧トランスデューサーを含め,すべてディスポーザルのものを用いています.下に,造影回路のセットを示します.トランスデューサー,三連活栓,耐圧造影チューブ,耐圧活栓がワンセットに包装されています.
| 当院で使用している造影回路の外観 | ||
| 発売元 | フクダ電子(株) | |
| 製造元 | (株)ウベ循研 | |
| 製品名 | CDX シリーズ ディスポーザルトランスデューサー | |
| 品番 | カタログNo. A265 | |
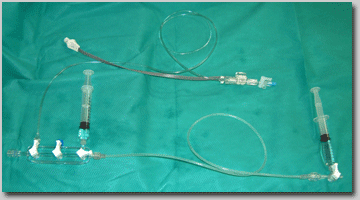 |
||
耐圧造影チューブは耐圧1,200 psiのものです.一般に市販されている耐圧造影チューブの中には,1回目の造影の際には1,000 psiに耐えられても,2回目以降には裂けてしまうものがあり,繰り返しの高圧注入を保証するものではないようです.
セットになっている三連活栓は900 psi程度で活栓から多少漏れ出す場合がありますが,造影上支障をきたす程ではありません.市販されている三連活栓の耐圧性については,耐圧ギリギリで使用した場合,各メーカーで問題の起こり方が異なります.何らかの問題のため耐圧以上の圧がかかった場合,三活の周りからじわじわと造影剤がしみ出るものはよいのですが,三活の中の部品(コックとT字型の回路部品)が勢いよくはずれて,吹き飛んでしまうメーカーがあり,事前に確認が必要と思われます.
ピッグテールカテーテルに直接接続する三活は,セットの中のトランスデューサーについている高耐圧のものを用い,代わりにトップのロック付き三活をトランスデューサーに取り付けます.CAG用のカテーテルに付ける三活は,トップまたはテルモのロック付き三活を使用しています.国産のロック付き三活(トップ,テルモ)は,耐圧については極めて優秀で,何の変哲もない普通のロック付き三活が800から900 psi以上の耐圧性能を持っています.また,三活の中の部品(コックとT字型の回路部品)も単なるはめ込みではなく,内圧が上昇すると外れにくくなる構造を持っているようです.
| 2. 圧トランスデューサー回路と造影回路のエアー抜き |
| 2-1 圧トランスデューサー回路のエアー抜き | ||
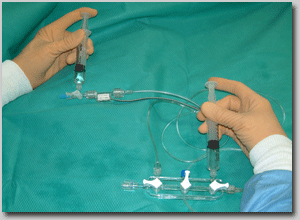 |
||
|
まずはじめに,圧トランスデューサー回路のエアー抜きをします.術野の外では改めてエアー抜きは行わないので,清潔な状態で,十分なエアー抜きを行います.
|
| 2-2 造影チューブ内のエアー抜き | ||
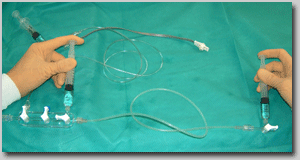 |
||
|
次に,造影チューブ内のエアー抜きをします.
|
| 2-3 圧トランスデューサーの接続 | ||||
|
||||
|
圧トランスデューサーを術野の外に手渡しします.ここでのエアー抜きは行わず,ゼロ調節を行うのみです.校正後は三活を閉じてもらいます.
|
| 2-4 インジェクターとの接続とエアー抜き | ||||
|
||||
|
インジェクターに回路を接続します.次に,インジェクターとシリンジ(ロック付き10ml)とのあいだで造影剤をやりとりします.3から4回造影剤をやりとりしますと,エアーは完全に除去されます.この部分のエアー抜きは後では行いませんので,完全に除去しておく必要があります.
|
| 2-5 造影チューブ内のエアー抜き | ||||
|
||||
|
造影チューブ内のエアー抜きを行います.前に一度行っているのですが,もう一度この作業をすることで,インジェクターに三活を取り付けた際に三活内に残るエアー(気泡)を除去することができます.
|
| 2-6 準備ができた造影回路の外観 | ||
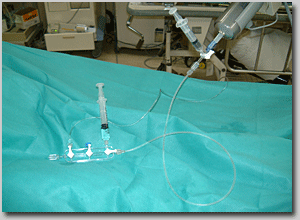 |
||
|
これで,造影回路の準備ができました.慣れると,1から2分で終了します.
|
| 3. カテーテルとの接続とエアー抜き |
| 3-1 造影カテーテルのエアー抜き | ||||
|
||||
|
3Frカテーテルのエアー抜きを行います.この際,一番気を付けなくてはならないことは,勢いよくシリンジで引きますと,気泡を発生してしまいますので,ゆっくり,じんわりと引いてくることが大切です.ここは時間をかけて注意して行わなければならないところです.皆さんご存じのこととは思いますが,接続部を指でたたきながら引いてくるのも当然ながら有効です.
|
| 3-2 カテーテルの接続と回路のエアー抜き | ||||
|
||||
|
カテーテルの三活を三連活栓のローテーターに接続します.次に,右の写真の様に,カテーテルの三活内部とローテーター内部のエアー抜きをします.
|
| 3-3 回路のエアー抜きの確認 | ||||
|
||||
|
三連活栓のシリンジを用い,ゆっくりと血液を引いてきます.ここで気泡が無いかどうかをしっかり確認します.特にローテーターは陽圧には強い構造になっていますが,陰圧ではローテーターのオー・リング(ゴム製のO型のパッキング)から空気を引き込みやすく,血液を引く操作の際には過度な陰圧をかけないような注意が必要です.
右の写真はローテーター内部からの気泡が引けてきたところです.この場合には,もう一度3-2と3-3のエアー抜きと確認の手順を気泡が引けなくなるまで繰り返します. |
| 3-4 再度のエアー抜き | ||||
|
||||
|
最後に,もう一度インジェクターの部分のシリンジを用いてゆっくりと血液を引いてきます.これでエアー(気泡)が無いことが確認されれば,エアー抜きは終了です.
インジェクターの部分のシリンジを用いたエアー抜きは,最初の造影の際だけに行えばよいと思います. |
| 3-5 先端圧の確認 | ||
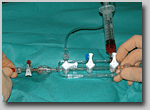 |
||
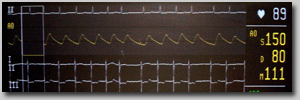 |
||
|
|
||
|
カテ先の血圧をモニターしているところです.このあと,造影を開始します.とにかく,高い圧力がかかりますので,すべての接続部分をしっかりとしめて,三活のコックがまっすぐになっているかをもう一度確認して下さい.
|
2005年2月20日記載